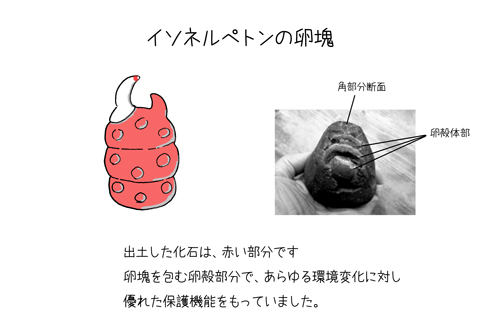ヒネルペトン(学名:Hynerpeton)は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州キャッツキル層から不完全な化石が産出している、後期デボン紀に生息した初期の四肢動物の属。当時のキャッツキル層は泥地の広がる熱帯域の河口であり、初期の四肢動物に適した環境であった。ヒネルペトンは体重支持能力を持つ四肢を有し、河川や河口において水陸両方の環境で過ごしていたと考えられる。指は8本であり、石炭紀のペデルペスやその後の四肢動物の5本を上回る。
歴史
1993年、古生物学者のエドワード・テッド・デシュラーとニール・シュビンはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ハイナー付近のレッド・ヒル化石サイトで最初のヒネルペトンの化石を発見した。彼らは四肢動物の起源の化石証拠を探すべくペンシルベニア州のデボン紀の岩石を調査している最中であった。最初に発見されたものは頑強な軟骨性左肩帯であり、強力な付属器官を持つ動物のものであった。化石はフィラデルフィア自然科学アカデミーに所蔵され、標本番号 ANSP 20053 に指定を受けた。1994年に『サイエンス』誌に掲載された論文中でデシュラーらは本属を命名し、上述の化石がホロタイプ標本に指定された。発見時点において、ヒネルペトンはアメリカ合衆国で発見された最古の四肢動物であった。また、レッドヒルに保存されていたような複雑な生態系の中に四肢動物が存在したことは、デシュラーとシュビンが四肢動物の起源と生態に抱いていた疑問のいくつかに答えをもたらすものでもあった。属名 Hynerpeton はハイナーおよび「這い回る動物」を意味する herpeton に由来する。後者のギリシア語の単語は新たに命名された太古の両生類に対して一般に接尾語として用いられる語である。種小名 bassetti はアメリカの都市計画者でありデシュラーの祖父でもあるエドワード・バセットへの献名である。
レッドヒル・サイトのうちもっとも化石に富む層である "Hynerpeton lens" は、本属にちなんで命名された。当該の地層は中期 - 後期ファメニアン期(約3億6500万年前 - 3億6300万年前)に堆積したと考えられている。1993年以降、Hynerpeton lens からは多くの堅頭類の化石が産出しており、肩帯・顎・頭蓋骨の断片・腹肋・大腿骨・上腕骨が産出している。2000年には1組の顎の骨が第二の属デンシグナトゥスに分類されている。他の研究によれば、このサイトにはさらなる未命名の分類群が多く存在しており、その中には最古のワトケエリア科の化石もある可能性があるとされる。
ヒネルペトン属に分類された化石はいくつかあるが、多くの場合においてその分類は訂正されている。例えば、古生物学者ジェニファー・クラックは1997年に行ったデボン紀の足跡化石の再検討に際し、追加の化石を本属に分類した。これらの化石はそれまで科学的文献で扱われたことがないもので、頬骨と腹部の鱗および下顎の部位が含まれていた。2000年にデシュラーはこの下顎 (ANSP 20901) をより詳細に記載し、デンシグナトゥスの化石と比較・対比した。2009年にデシュラーとクラックおよびシュビンはレッドヒルの四肢動物化石についてより包括的な再検討を行い、オリジナルの軟骨肩帯が発見された場所との近接性に基づき、大部分の化石をヒネルペトン属に分類した。しかし彼らは、当該地点の付近には特徴的な上腕骨を持つワトケエリア科のデンシグナトゥスをはじめとする他の固有の動物がおり、近接性はこの分類を有効と考える十分な根拠ではないとも主張した。このため彼らは Clack (1997) と Daeschler (2000) で記載された標本がヒネルペトン属の保証が無いものと判断した。ただし、ANSP 20054 という左擬鎖骨については、ホロタイプと実質的に等しい形態をしていることから本属に分類している。
形態
ヒネルペトンの個体はイクチオステガやアカントステガといった他の初期の四肢動物に類似していたと考えられる。ヒネルペトンの解剖学的特徴について特定の結論を導くには化石があまりにも欠如しているが、保存された軟骨性肩帯の構造から、その分類に関する情報は提示されている。軟骨性肩帯は肩甲骨・烏口骨・擬鎖骨の部位を含むが、鎖骨と間鎖骨を含まない。肩帯の全体的な形状は頑強かつ肉切り包丁状である。大部分の有羊膜類で喪失した刃状の骨である擬鎖骨は、ヒネルペトンにおいて上側に突出する骨体を形成する。後側に突出するブレードは、肩甲関節窩を持つ板状の骨である肩甲烏口骨で構成される。この骨は後の四肢動物では肩甲骨と烏口骨に分かれていくことになる。ユーステノプテロンといった肉鰭類において軟骨性の肩帯は頭蓋骨に付着するが、真の四肢動物の軟骨性肩帯は擬鎖骨と肩甲烏口骨の2つに分かれる。ヒネルペトンの肩帯は両者の中間型であり、肩帯は頭蓋骨からは離れているものの、まだ2つの骨に区分されてはいない。このため、ヒネルペトンは石炭紀まで化石記録が確認されていない真の四肢動物よりも、デボン紀のステム四肢動物と共通している。骨の大きさに基づくと、ヒネルペトンの推定全長は約0.7メートルである。
擬鎖骨の部位は滑らかであり、四足形類が持つ粗いテクスチャの擬鎖骨とは異なる。加えて、擬鎖骨の上部は拡大していてかつ僅かに前側へ傾斜する。これはチュレルペトンや真の四肢動物との共有派生形質である。肩甲烏口骨の領域は側面から見た際に大きいが、腹側から見ると非常に薄い。肩甲関節窩は肩甲烏口骨の後外側縁に位置し、チュレルペトンを除く他のデボン紀の四肢動物よりも顕著に外側に位置している。上記の肩甲関節窩は隆起しており、supraglenoid buttress としても知られる。
ヒネルペトンには複数の固有派生形質もある。肩甲烏口骨の内側面には肩甲下窩として知られる大きな深い窪みが存在する。この窪みの上側の縁は筋痕に被覆されているため、テクスチャが粗い。一方で肩甲下窩の後側の縁は大きく隆起した領域で構成されており、この領域は infraglenoid buttress として知られる。また関節下窩として知られる第二の窪みが肩甲関節窩と連続しており、骨の後側を包むようにして infraglenoid buttress を二等分する。
これらの形質の組み合わせから、ヒネルペトンの軟骨性肩帯肩のうち甲烏口骨部分には強靭な筋肉が付着していたことが示唆される。関節下窩は本属において特に卓越する部分であり、後引筋の起始点であった可能性もある。この骨の前側縁には同様の溝があり、四肢の挙上や伸展に寄与した可能性がある。肩甲下窩の縁にも筋肉の付着部が明らかに存在する。これらの特徴が他のステム四肢動物やクラウン四肢動物では知られていないため、ヒネルペトンの筋肉はデボン紀以降に継承されない固有の運動に用いられていた可能性が高い。記載者らは、強靭な筋肉のためヒネルペトンが遊泳も歩行も可能であったことを提唱している。
他の同時代の生物と異なり、ヒネルペトンは鰓孔列後葉 (postbranchial lamina) を欠く。この骨のブレードは多くの魚類やアカントステガをはじめとするいくつかのステム四肢動物で保存されており、擬鎖骨の内側縁に沿って長さ方向に伸びる。典型的にこの構造は鰓室の後側の壁を形成し、鰓を通る水の長さが一方向に定めることに寄与する。ヒネルペトンにこの構造が存在しないことは、本属に鰓室が存在しない可能性、さらには本属の系統がこの適応を遂げた最初期の脊椎動物の一つであった可能性を示唆する。しかし、この解釈には議論もある。Janis & Farmer (1999) は鰓孔列後葉がいくつかのトリスティコプテルス科魚類に存在しないこと、またワトケエリアに存在することを指摘した。Shoch & Witzmann (2011) は鰓孔列後葉が保存された時期や過程は数多くの堅頭類の擬鎖骨が適応放散を遂げているため必ずしも明らかではないと指摘している。加えて彼らは、外鰓で呼吸する水棲の有尾目が鰓孔列後葉を必要としないことも指摘している。Daeschler et al. (1994) は、鰓孔列後葉が存在しないことについて、ヒネルペトンがアカントステガよりも進化的であることを示す派生的特徴であると考えた。それに反し、Schoch & Witzmann (2011) は分椎目のトレマトレステスやプラギオスクスといったクラウン四肢動物においても鰓孔列後葉の証拠があることを指摘した。このため、ヒネルペトンの鰓孔列後葉の喪失はクラウン四肢動物とは独立に進化したものである可能性が高い。
分類
1994年の原記載において、ヒネルペトンは暫定的に四肢動物のイクチオステガ目に分類された。当時、四肢動物は4本の手足を持つ全ての脊椎動物を指し、イクチオステガに類似する「原始的」なデボン紀の動物を指していた。しかし、分岐学の台頭に伴ってこれらの用語は変化した。多くの古生物学者は「四肢動物」の従来的な定義を使用し続けたが、一部の古生物学者は分岐学的な定義を用い始めたのである。その新たな定義とは、現生四肢動物の最も近い共通祖先の子孫のみに絞るクラウングループのみに「四肢動物」という語の範囲を制限するものであった。ヒネルペトンは4本の手足を持つという意味では四肢動物であるが、現生の四肢動物が進化する遥か以前に絶滅した系統であるため、四肢動物のクラウングループには属さない。同様に、イクチオステガ目は類縁関係に基づく系統群ではなく、真の四肢動物に繋がる進化的段階を示す段階群であったため、分岐学の時代には用いられない用語となった。四肢動物の伝統的な非分岐学的定義は最初期の手足のある脊椎動物から始まるものであるが、これはパンデリクチスよりも分椎目に近縁な全ての動物として定義された系統群である堅頭類とほぼ等しい。
化石の産出部位が限られているため、ヒネルペトンが系統解析の内群に選ばれることは稀である。ヒネルペトンを加えた数少ない解析では、本属はクラウン四肢動物に繋がる一連のステム四肢動物の遷移的な形態の一つとして位置付けられている。擬鎖骨の形状と鰓孔列後葉の喪失のため、本属はアカントステガ、および大抵の場合はイクチオステガよりも派生的な位置に置かれる。その一方、軟骨性肩帯が一つに癒合していることから、本属がチュレルペトンよりも派生的な位置に置かれることは無い。以下は Ruta, Jeffery & Coates (2003) に基づくクラドグラムを単純化したもの。
古環境
ヒネルペトンはペンシルベニア州のレッドヒル・サイトで発見された。この切土では、太古の沿岸の氾濫原が広がっていたキャッツキル層のダンカノン部層の化石が保存されている。後期デボン紀当時のこの氾濫原は赤道に近く、そのため気候は温暖湿潤であり、雨季と乾季が存在した。キャッツキル層はユーラメリカ大陸を二分する浅海域の沿岸に形成されており、小規模で流れの遅い河川が大陸東部のアカディア山脈から流れていた。これらの河川はその流路を劇的に変えやすく、河川流路の近傍には三日月湖を形成した。最も豊富な植物は広い葉を持つ太古の植物(アルカエオプテリス)の森林であり、シダ様植物(ラコフィトン (Rhacophyton))が湿地に繁茂していた。乾季には山火事が日常茶飯事であり、証拠として炭化したラコフィトンが大量に発見されている。他の植物にはレピドデンドロプシス (Lepidodendropsis) やオツィナコソニア (Otzinachosonia) といったヒカゲノカズラ綱のほか、バリノフィトンやギレスピエア (Gillespiea) といった分類の難しい草本類がある。
レッドヒルの動物も極めて多様である。レッドヒル動物群の節足動物の一部には、初期のクモ綱であるギガントカリナス (Gigantocharinus)、ヤスデのオルサデスムス (Orsadesmus)、未記載のサソリがいる。河川には多様な魚類が生息していた。底生の板皮類には少数のフィロレピスのほか、一般に見られるものとしてグロエンランダスピスがおり、魚類群集の大部分を占めるものとして化石の豊富なトゥリサスピスが知られている。初期の条鰭類であるリムノミス (Limnomis) も化石が豊富であり、大規模な魚群を形成していた可能性が高い。初期のサメも存在が確認されており、極めて小さいアゲレオドゥスや鰭に棘を伴うクテナカンサスがいた。氾濫原には多様な肉鰭類が生息していただけでなく、大型棘魚類であるギラカンタスも知られている。これらの動物群集の頂点捕食者はハイネリアであり、全長3メートルに及ぶ肉鰭類であった。
ヒネルペトンはこのサイトから報告された唯一の四肢動物というわけではなく、より大型の属であるデンシグナトゥスも共存していた。加えて、ヒネルペトンの軟骨性肩帯と合致しない1本の上腕骨が発見されており、この氾濫原に第三の属が生息した可能性が示唆される。ペデルペスやワトケエリアといったワトケエリア科のものに類似した頭蓋骨の断片も第四の属が生息した可能性を示唆するが、これらの化石をワトケエリア科に分類することには疑問の声も上がっている。レッドヒル・サイトの堆積環境と動物相からは、ステム四肢動物が陸上進出を遂げた理由と過程に関する疑問に対し、新たな仮説がもたらされている。キャッツキルの氾濫原は河川が完全には乾燥しきらなかったが、年に数回は浅い池が主要な河川から孤立したのである。大型肉食魚は深い河川を遊泳するため、陸棲動物あるいは半水棲動物はこれらの池を捕食者からの避難所として利用できたのである。現在の地球では、オーストラリアのマレー川に類例を見ることができる。雨季と乾季を経験するこの亜熱帯の現代環境では、抱卵するゴールデンパーチ (Macquaria ambigua) は、河川の主要部に居る大型で俊敏なマレーコッド (Maccullochella peeli) から逃れるため河川の湾曲部へ避難する。デボン紀の環境では、上陸能力を持つ脊椎動物はこれらの異なる環境の間を移動する際にアドバンテージがあった可能性がある。また、こうした生態がもたらす柔軟性によって、彼らはより多様な食料源を活用できた可能性もある。
出典